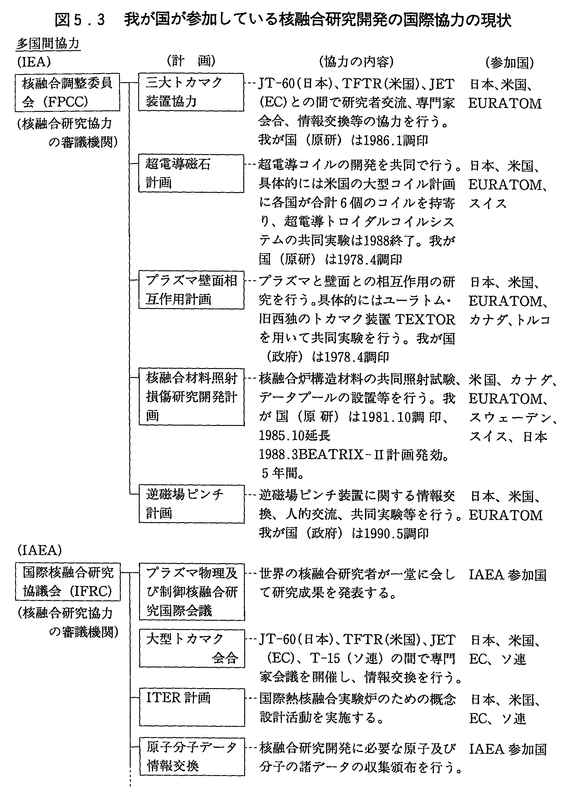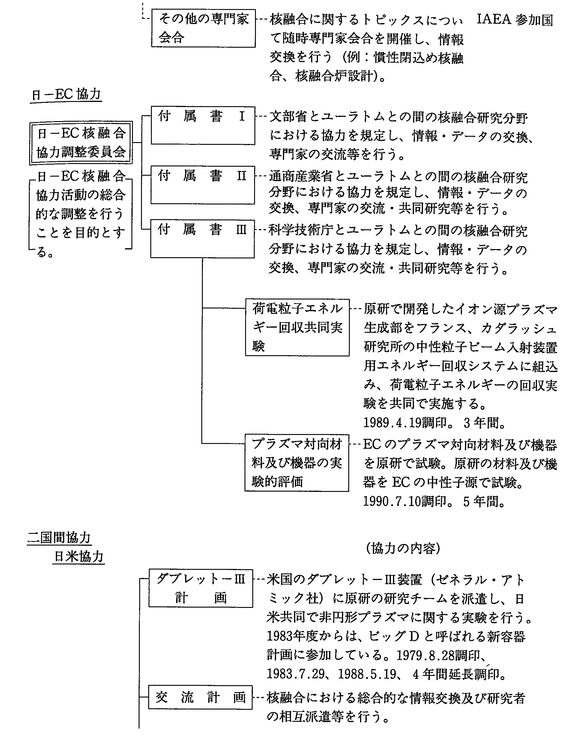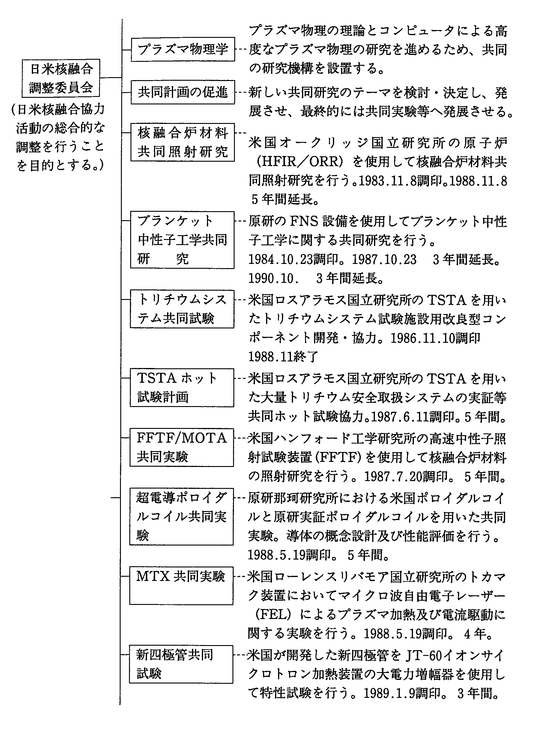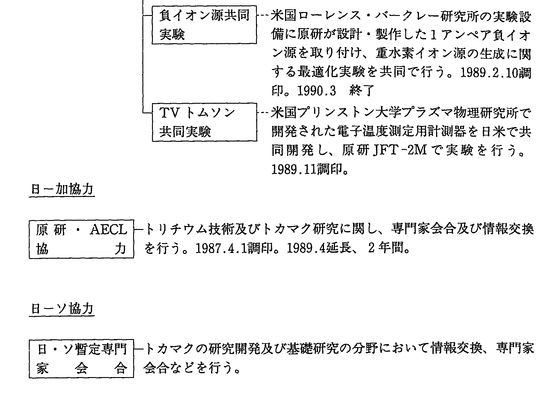1.核融合
(3)国際協力
現在,我が国が進めている国際協力としては,日米等の二国間協力と国際原子力機関(IAEA)及び国際エネルギー機関(IAEA)における多国間協力がある。
①日米協力
日米協力については,1979年5月に締結された日米エネルギー研究開発協力協定において核融合が協力の重点分野の一つとされ,ダブレット―III(非円形トカマク試験装置)を用いた研究を始めとする共同研究,情報交換及び研究者の相互派遣等を行う交流計画,プラズマ物理の共同研究並びにダブレット―III共同研究の他,核融合炉材料,加熱技術,超電導コイル等の分野で協力が行われている。
なお,日米エネルギー研究開発協力協定は9ケ月間の暫定延長の後,1990年2月1日に一部修正の上,5年間の協力延長を行った。
②日EC協力
日・EC間では1989年2月に政府間レベルの日・EC核融合協力協定が署名されたことを受け,1989年4月,原研-カダラッシュ研(仏)との加熱装置に関する共同実験等,本格的研究協力が開始された。
③IAEAにおける協力
IAEAにおける協力については,プラズマ物理及び制御熱核融合研究国際会議,大型トカマク会合,原子分子データ情報交換に関する協力等に積極的に参加している。
また,1985年の米ソ首脳会談において熱核融合の実用化に向けての国際協力の重要性が強調されたのを受け,1988年4月よりIAEAの支援の下に日,米,EC,ソ連の4極により,国際熱核融合実験炉(ITER)の概念設計に関する協力活動が開始され,同活動は1990年に成功裏に終了した。
引き続き,工学設計活動の協力を行うことについて4極間で協議が行われ,1991年7月,共同設計チームを日,米,ECの3ヵ所に設置すること等について実質的な合意が達成された。これを受けて,各極における国内手続き等の完了を待って,工学設計活動が開始されることとなる。
④IEAにおける協力
IEAにおける協力については,三大トカマク協力,超電導磁石計画,プラズマ壁面相互作用計画,核融合材料照射損傷研究開発計画及び逆磁場ピンチ計画の協力に積極的に参加している。
目次へ 第5章 第2節(1)へ