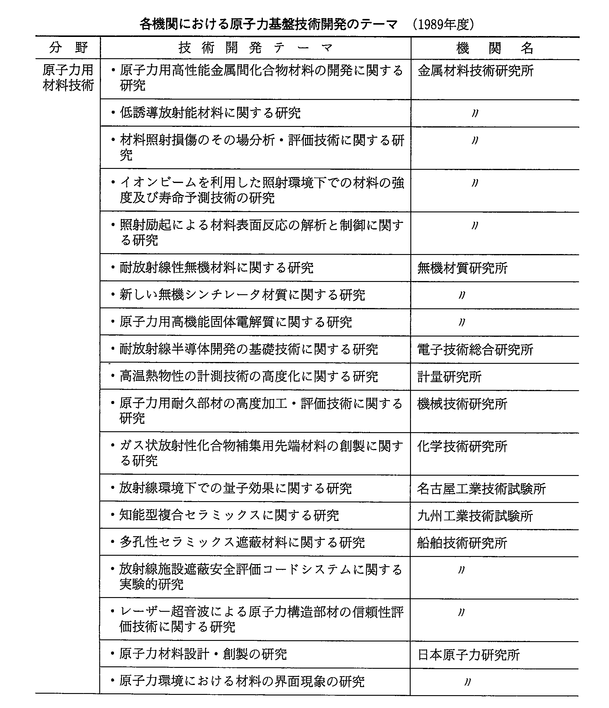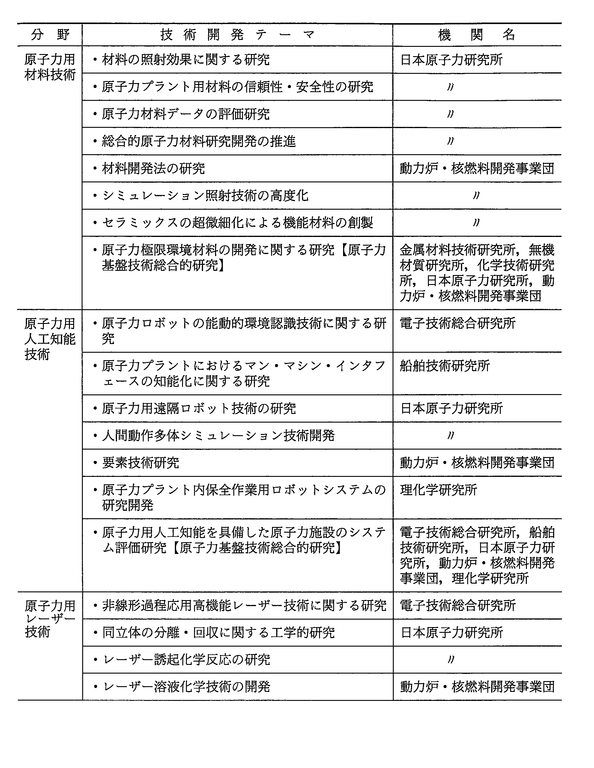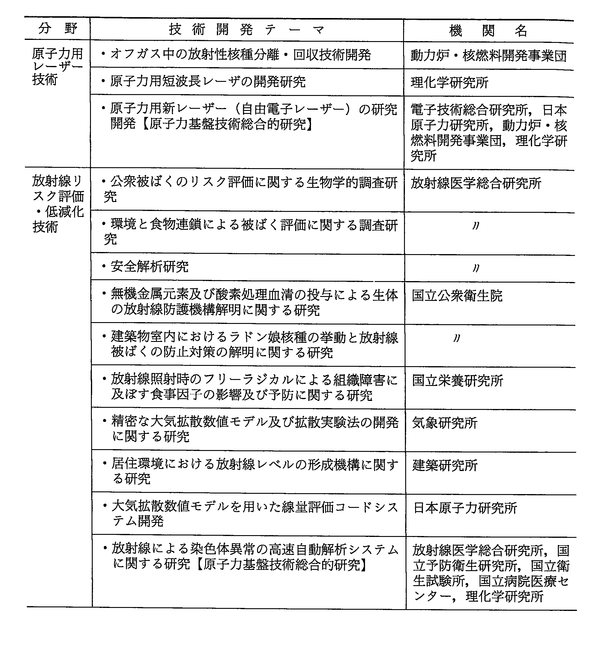2.基盤技術開発
1987年6月に策定された原子力開発利用長期計画においては,創造的科学技術の育成が基本目標の一つに掲げられ,この中で基礎研究の充実,先導的プロジェクト等の効率的推進とともに,基盤技術開発の重点的推進を図ることとしている。これを受け,1987年9月に原子力委員会に設置された基盤技術推進専門部会は1988年9月に報告書をとりまとめ,原子力開発利用長期計画に提示された原子力用材料技術,原子力用人工知能技術,原子力用レーザー技術,放射線リスク評価・低減化技術の4領域のそれぞれについて推進すべき,研究開発テーマを具体的に示した。
基盤技術開発は,1988年度から日本原子力研究所,動力炉・核燃料開発事業団,理化学研究所及び,国立試験研究機関において,上記の報告書に沿った技術開発が行われている。
また,原子力基盤技術のうち,各研究機関がポテンシャルを結集して行う必要があるものについて,日本原子力研究所,動力炉・核燃料開発事業団などの各研究機関の積極的な研究交流により研究開発を推進する「原子力基盤技術総合的研究」を,1989年度から開始している。
以下に各領域の研究内容について示す。
(1)原子力用材料技術原子力用材料技術については,金属系材料,セラミックス系材料,高分子・有機系材料及び複合材料等の新しいタイプの耐放射線性材料,放射線を低減化するための材料の創製,その諸特性の機構解明,ミクロレベルの材料解析・評価を行うとともに,原子力複合極限環境下での材料の化学反応・制御,原子力用材料データ・ベースの構築に関する研究開発等が技術開発課題となる。
このうち,材料照射損傷その場分析・評価装置を用いた原子レベルで起こる照射損傷の過程を解明するための技術開発等が金属材料技術研究所で,耐放射線性無機材料に関する研究等が無機材質研究所で,耐放射線性半導体の開発に関する基礎技術については電子技術総合研究所で実施されているなど,計9国立試験研究機関で技術開発が実施されている。
また,材料の中性子等の照射効果に関する研究等が日本原子力研究所で,高速増殖炉や再処理プラントなど核燃料サイクル全般のプラント材料に要求される耐放射線性構造材料の開発が動力炉・核燃料開発事業団で実施されている。
さらに,「原子力基盤技術総合的研究」として,原子力極限環境材料の開発に関する研究が,金属材料技術研究所,無機材質研究所,化学技術研究所,日本原子力研究所及び動力炉・核燃料開発事業団において実施されている。
(2)原子力用人工知能技術原子力用人工知能技術については,人間の運転・保守等を支援するシステムを伴ったプラントを中間的な目標とし,究極的には自己判断・制御を行う自律型プラントを目指し,知識ベース・システム技術,情報収集・処理技術,ロボット技術,シミュレーション技術,マン・マシン・インタフェース技術が技術開発課題となる。
このうち,原子力に用いられるロボットの環境認識技術等の研究開発が電子技術総合研究所で,プラント運転用のマン・マシン・インターフェイスの知能化に関する研究が船舶技術研究所でそれぞれ実施されている。
また,高線量下で働くロボットの動作・判断を高度にシミュレーションする技術等の研究開発が日本原子力研究所で,原子力プラントの運転管理・制御・診断等への知的機能付与に関する研究開発が動力炉・核燃料開発事業団で,人間の保全作業のロボット化の研究が理化学研究所で実施されている。
さらに,「原子力基盤技術総合的研究」として,原子力用人工知能を具備した原子力施設のシステム評価研究が,電子技術総合研究所,船舶技術研究所,日本原子力研究所,動力炉・核燃料開発事業団及び理化学研究所で実施されている。
(3)原子力用レーザー技術原子力用レーザー技術については,同位体・元素等の分離,レーザー計測・分析等の原子力用レーザー応用技術,高出力,波長可変,高繰返し等原子力への応用に必要なレーザー技術,レーザー物理,化学利用技術など原子力に新たな利用の可能性を与えるレーザー技術が技術開発課題となる。
このうち,各種非線形光学過程利用による波長変化及び短パルス化が電子技術総合研究所で実施されている。
また,レーザー光・放射線複合照射による有機化学反応の選択性等の研究が日本原子力研究所で,レーザー光を利用した酸化還元反応による再処理工程技術の高度化,再処理工程のオフガス中の放射能気体に関する研究が理化学研究所で実施されている。
さらに,「原子力基盤技術総合的研究」として,波長可変かつ高出力が得られる自由電子レーザーの開発が,電子技術総合研究所,日本原子力研究所,動力炉・核燃料開発事業団,及び理化学研究所で実施されている。
(4)放射線リスク評価・低減化技術放射線リスク評価・低減化技術については,放射性核種の環境中での挙動,生体内代謝,挙動解析技術からなる被ばく線量評価技術,発がん,発生障害,遺伝的リスク等の放射線リスク評価技術,発生原因回避除去,生物学的低減化技術からなる放射線リスク低減化技術が技術開発課題となる。
このうち,低レベル放射線による発がん等の影響,分子・細胞生物学的にみた放射線による発がんの機構,日本人の特徴を考慮に入れた公衆の被ばく線量の評価等の研究が放射線医学総合研究所で,放射性物質の精密な大気拡散数値モデル等の開発に関する研究が気象研究所で実施されているなど,計5国立試験研究機関で関連の研究が実施されている。
また,放射性物質の大気拡散について,広域高層の範囲につき高精度化を目指したコードシステムの技術開発が日本原子力研究所で実施されている。
さらに,「原子力基盤技術総合的研究」として,放射線による染色体異常の高速自動解析システムに関する研究が,放射線医学総合研究所,国立予防衛生研究所,国立衛生試験所,国立病院医療センダー及び理化学研究所で実施されている。
目次へ 第7章 第3節へ