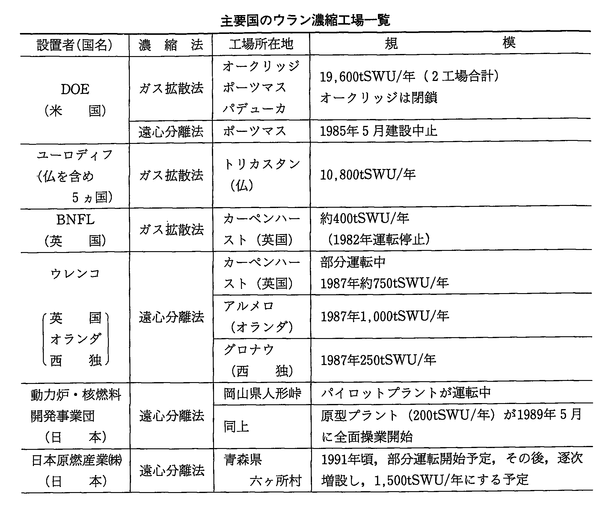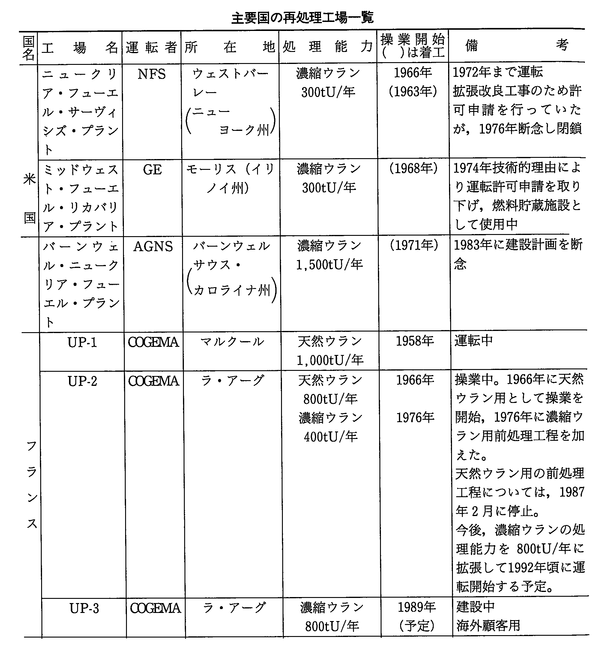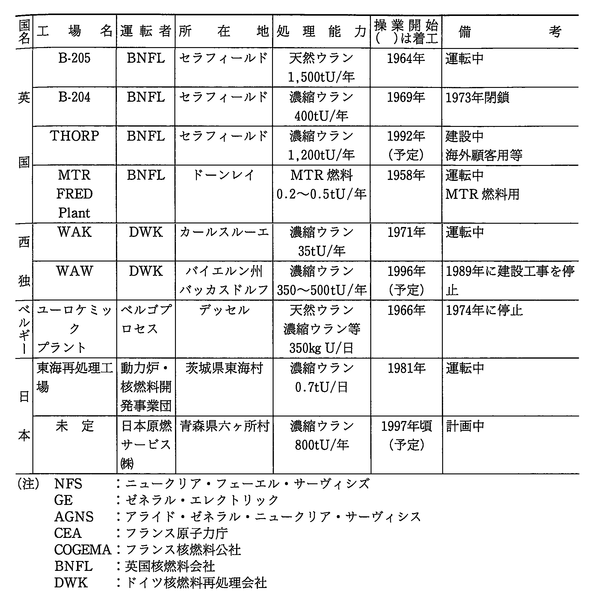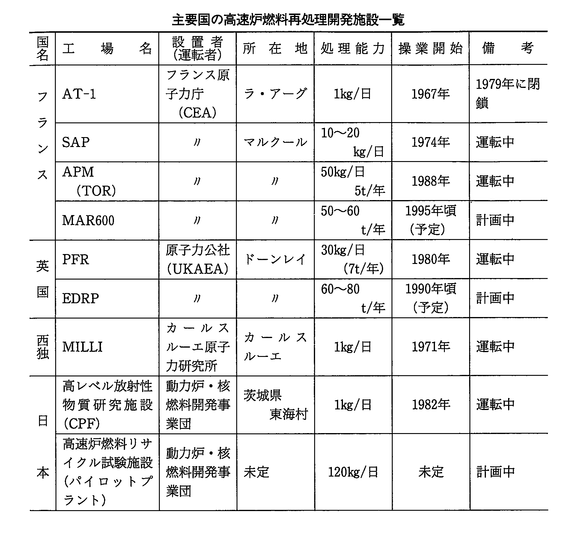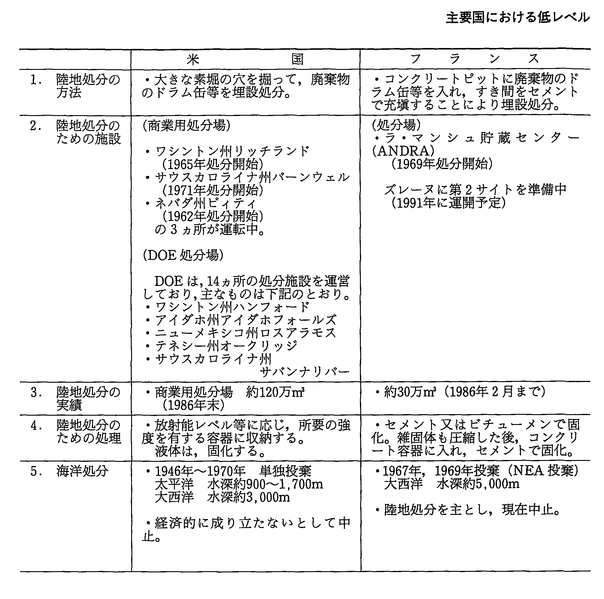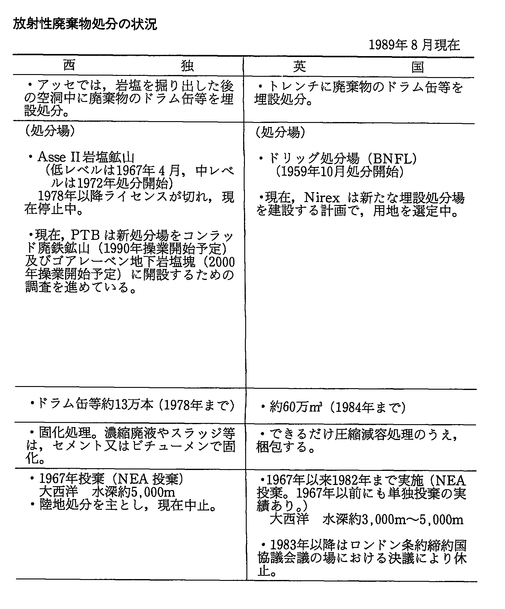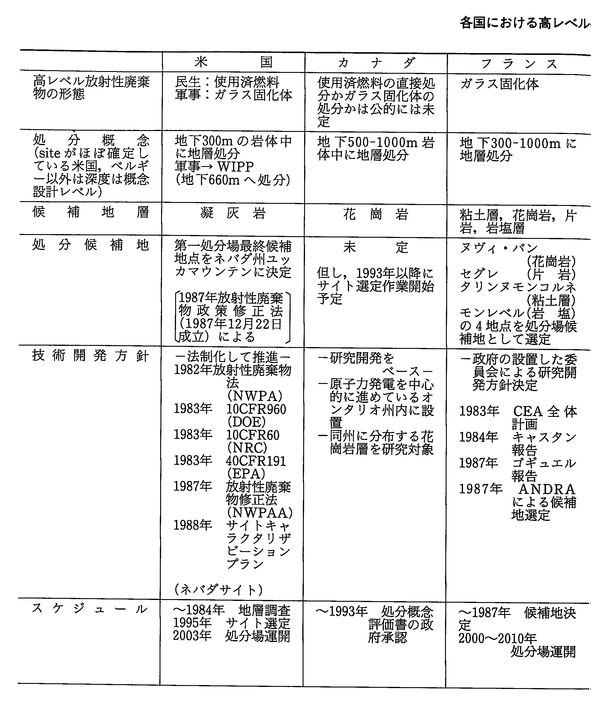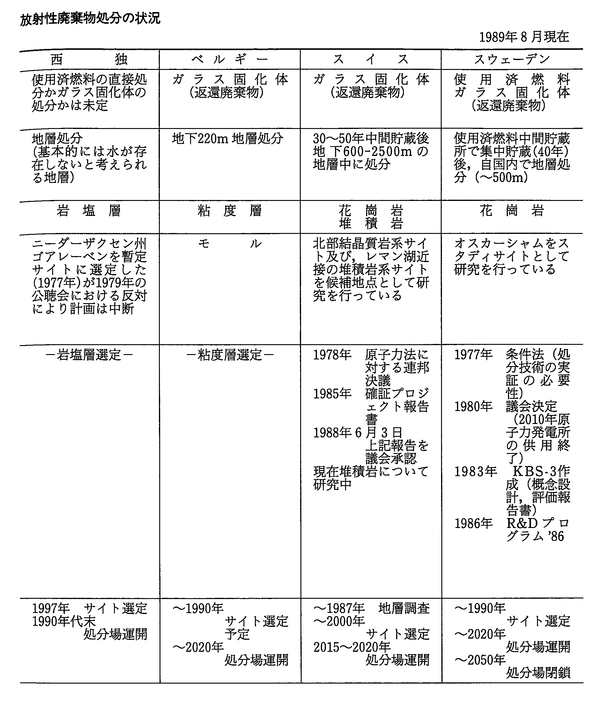(参考)諸外国の動向
(1)ウラン濃縮
①米国
米国のウラン濃縮工場は,米国エネルギー省(DOE)が所管し,現在,ガス拡散法による2工場がポーツマス,パデューカにおいて運転されており,オークリッジ工場は1987年12月に閉鎖が決定された。
米国2工場の濃縮規模は合計で19,600トンSWU/年となっている。
なお,DOEは1985年6月に将来の濃縮技術の開発を原子レーザー法(AVLIS)一本に絞り,これにより早期の実用化をめざすとともに,当面は,ガス拡散工場の運用の合理化等で対処する旨の新政策を発表したが,その後の展開は,DOEのAVLIS開発を含む濃縮事業部門全般の民営化の動向とも関連し,やや流動的となっている。
②フランス
フランスではユーロディフ計画(フランス,イタリア,スペイン,ベルギー,イランの共同濃縮事業)に基づき,ガス拡散法による工場がトリカスタンにおいて運転されており,その濃縮規模は10,800トンSWU/年となっている。また,将来の濃縮技術として,原子レーザー法を中心とする研究開発が積極的に進められている。
③英国
英国のウラン濃縮工場は,英国核燃料会社(BNFL)が所管し,カーペンハーストにおいてガス拡散法による工場と遠心分離法による工場の2工場が運転されていたが,ガス拡散法による工場(約400トンSWU/年)は1982年9月,運転を停止している。遠心分離法による工場はウレンコ計画(英国,西独,オランダの共同濃縮事業)に基づくもので,1987年までに約750トンSWU/年に拡張された。
④西独
西独は,現在,ウレンコ計画に基づき,グロナウに遠心分離法による濃縮工場が1985年8月に運転開始し,1987年には250トンSWu/年の濃縮規模となっている。
⑤オランダ
オランダは,ウレンコ計画に基づき,アルメロに遠心分離法による濃縮工場の建設・運転を行っており,1987年には濃縮規模は約1,000トンSWU/年となっている。
(2)再処理
①米国
米国の再処理工場については,モーリスの工場が1974年に,ウェストバレーの工場が1976年に運転を断念し,またバーンウェルの工場が1983年に建設計画を断念した。
②フランス
フランスの再処理工場は,マルクールとラ・アーグの2ヵ所にある。マルクールでは,1958年以来天然ウラン1,000トンU/年の処理規模のUP-1工場が運転中であり,1987年6月までに累計約3,000トンの使用済燃料を処理している。
ラ・アーグでは,1967年から天然ウラン800トンU/年の処理規模のUP-2工場が運転中である。同工場は,1976年に軽水炉燃料処理のための前処理工程等(処理規模:軽水炉燃料400トンU/年)を増設し,以来ガス炉燃料及び軽水炉燃料を再処理しており,1988年3月までに累計約7,100トン(うち軽水炉燃料2,200トン)の使用済燃料を処理している。なお,同工場では,1987年2月にガス炉燃料の再処理を終了しており,現在は,軽水炉燃料専用の再処理工場として稼働している。
さらに,現在軽水炉燃料の再処理規模を拡大するため,1992年の運転開始を目指し,新たな前処理工程等の建設が行われており,完成すると処理規模は軽水炉燃料800トンU/年に増強される予定である。
また,外国からの委託再処理のためUP-3工場(処理規模:軽水炉燃料800トンU/年)を1989年末の運転開始を目指し,ラ・アーグに建設中である。
③英国
英国の再処理工場は,英国核燃料会社(BNFL)が所管し,セラフィールドに天然ウラン燃料を再処理するため処理規模1,500トンU/年の工場が運転中である。また,セラフィールドにおいて外国から委託再処理のため1992年頃の運転開始を目指し,THORPプラント(処理規模:軽水炉燃料1,200トンU/年)の建設を進めている。
④西独
西独では,主要電力会社12社が設立したドイツ核燃料再処理会社(DWK)が原子力発電所から発生する使用済燃料の再処理を実施することとなっている。
DWK社は,カールスルーエに再処理用実験プラントであるWAK(処理規模:軽水炉燃料35トンU/年)の運転経験を有し,さらにWAKの運転経験を基に,バイエルン州バッカスドルフにおいて1996年頃の運転開始を目途に350~500トンU/年規模の再処理工場の建設を進めていたが,再処理はフランス等との協力で行う方針の下,WAWについては1989年6月,再処理工場建設工事の停止を決めている。
(3)高速炉燃料再処理高速炉燃料再処理の開発については,おおむね高速炉の開発と並行して進められているが,フランス,英国ではパイロット規模の施設が,西独,日本では実験室規模の施設が既に運転中である。
①フランス
ラ.アーグのAT-1プラントが1967年から1979年まで運転された。現在,マルクールでSAPプラント(10~20kg/日)が運転中であり,さらにTORプラント(50kg/日〔5トン/年〕)への改造・増設が行われ,APMと改称され1988年1月から処理が開始された。
その後の施設としてMAR-600(50~60トン/年)と呼ばれる新施設が計画されている。
② 英国
ドーンレイにおいて既に30kg/日 (7トン/年)のプラントが1980年より運転中で,将来的にCDFR計画に対応した60~80トン/年のプラントが計画中である。
③ 西独
カールスルーエにおいて,1kg/日の実験施設が1971年より運転中である
(4)放射性廃棄物処理処分
①米国
使用済燃料のままでの処分(地層処分)が考えられているが,軍事用等の高レベル廃液については,ガラス固化し,貯蔵した後,地層処分する計画である。他方で,種々の固化法についての研究開発も行っている。
低レベル放射性廃棄物は,バーンウェル,リッチランド,ビィティの3つの民間の処分施設において陸地処分を行っているほか,DOE関係施設からのものは,主に連邦政府運営の処分施設において陸地処分を行っている。
また,1982年核廃棄物政策法が成立し,米国における高レベル放射性廃棄物対策の基本枠組が示された。DOEは,この法律(1987年12月一部修正)にしたがって,2003年の地層処分開始を目標に,現在ネバダ州ユッカマウンテンにおいてサイト特性調査を実施中である。
②フランス
使用済燃料を再処理し,高レベル廃液は,ガラス固化し,貯蔵した後,地層処分する計画であり,ガラス固化法としては,AVM(AtelierVitrificationdeMarc-Oule)法*が実用段階であり,マルクールにおいて,1987年よりガラス固化体を製造し貯蔵している。また,1989年末頃の運転開始を目途に,実用規模の固化プラントがラ・アーグに建設中である。
地層処分については,政府の放射性廃棄物管理局(ANDRA)が責任を負い,ANDRAは,1987年2月~3月に4つの処分場候補地(岩種は,花崗岩,粘土岩,結晶片岩,岩塩の4種類)を選定した。
低レベル放射性廃棄物は,ラ・マンシュ貯蔵センターで陸地処分を実施している。また,ラ・マンシュ貯蔵センターに次いで第2処分場として,オーブ県スレーヌにおいて,オーブ貯蔵センターが現在,建設中であり,1991年より操業開始を予定している。
*AVM法:フランスが開発したガラス固化法で,高レベル廃液をロータリーキルンで熾焼し,ガラス粉末を加えて溶融炉で高周波加熱により溶かした後,キャニスターに封入する方式である。
③英国
使用済燃料を再処理し,高レベル廃液は,ガラス固化して,貯蔵した後,地層処分する方針であり,ガラス固化法としては,AVM法を採用することを決定している。
低レベル放射性廃棄物は,ドリッグ処分場にて陸地処分を行っているほか,海洋処分の実績も有している。
また,1982年7月,Nirex**(Nuclear Industry Radioactive Waste-Executive)と呼ばれる低・中レベル放射性廃棄物の処理処分を実施する新たな機関を設立した。
④西独
高レベル廃液は,ガラス固化して,貯蔵した後,ゴアレーベン(岩塩)に地層処分する計画であり,処分の責任は連邦物理技術院(PTB)が負う。
ガラス固化法としては,LFCM法***(Liquid Fed Ceramic Melter)がベルギーと共同で開発され,プラントが運転されている。
低レベル放射性廃棄物については, AsseII(岩塩坑)において1967年から1978年まで陸地処分を実施したが,その後許可手続の関係で中断している。替わってPTBは新処分場をコンラッド廃鉄鉱山及びゴアレーベン地下岩塩塊に開設するための調査を進めている。
**Nirex:原子力産業放射性廃棄物執行部。
英国原子力公社(UKAEA),英国核燃料会社(BNFL)及び電気事業当局(CEGB SSEB)により,それらの代理機関として設立され,低・中レベル廃棄物の処理処分を実施する。
***LFCM法:高レベル廃液を脱硝,濃縮し,ガラス原料を加えてセラミック製の溶融炉で直接通電により溶かし固化する方法であり,動力炉・核燃料開発事業団が,建設している固化プラントにおいても採用することとしている。
⑤スイス
使用済燃料は,すべて外国で処理し,返還されるガラス固化体を国内で地層処分する計画である。処分の責任は,電力会社と連邦政府の共同出資で設立された放射性廃棄物全国貯蔵組合(NAGRA)が負い, NAGRAはスイス北部の花崗岩地帯の12地点で処分場選定のためのボーリング調査等を実施している。一方,処分のための研究は南アルプスのグリムゼル岩盤研究所で深地層試験を実施中である。
⑥スウェーデン
使用済燃料のままで,地下式集中貯蔵施設において40年間程度貯蔵の後に地層処分する計画である。処分は,4つの電力会社が出資して設立したスウェーデン核燃料・廃棄物管理会社(SKB)が行うことになっている。
ストリパ鉱山(現在,廃坑)を使って,高レベル放射性廃棄物の地層処分に関するプロジェクト(ストリパ計画)が, OECD/NEAの枠組みの中で進行中であり,我が国からは動力炉・核燃料開発事業団が参加している。
⑦カナダ
放射性廃棄物の処理処分についてはカナダ原子力会社(AECL)が中核となり研究開発を行っている。
使用済燃料を直接処分するか,再処理してガラス固化体にするかはまだ決まっていない。AECLはマントバ州ウィンペグに,地下研究施設を設置して,高レベル放射性廃棄物の地層処分の研究開発を実施している。我が国との研究協力については,日本原子力研究所及び動力炉・核燃料開発事業団とAECLの間で,高レベル放射性廃棄物の処理処分に関する研究協力が行われている。
⑧ベルギー
使用済燃料はフランスに再処理委託し,その返還ガラス固化体を国内で地層処分する計画である。
放射性廃棄物の処理処分の研究開発については,モル原子力研究センター (SCK/CEN)を中心に行われている。一方,放射性廃棄物の処理処分の実施については放射性廃棄物・核分裂性物質国家機関(NIRAS/ ONDRAF)が1980年に設立されている。動力炉・核燃料開発事業団とモル原子力研究センターの間で高レベル放射性廃棄物地層処分に関する研究協力が行われている。
⑨オーストラリア
高レベル廃液の処理方法として,合成岩石中に放射性核種をとじ込めるシンロック固化法について研究開発を行っている。1984年5月には我が国との研究協力に関する口上書を交換しており,オーストラリア原子力科学技術機構(ANSTO)と日本原子力研究所を中心とした研究協力が行われている。
目次へ 第3章 第1節へ