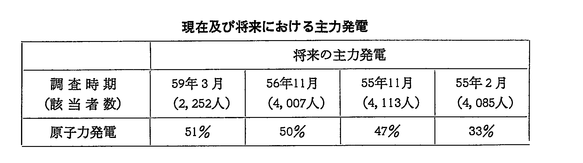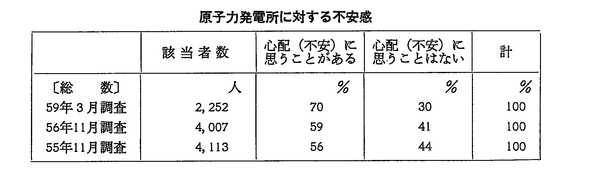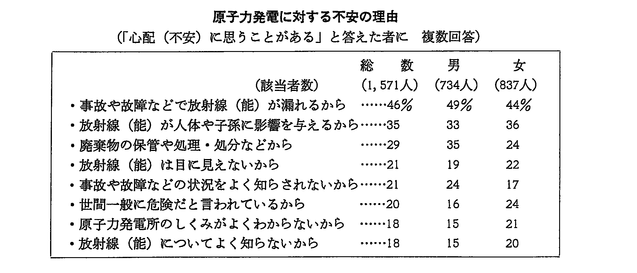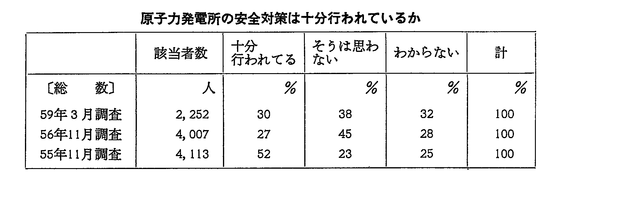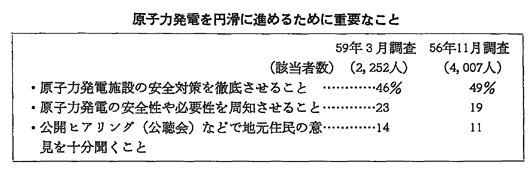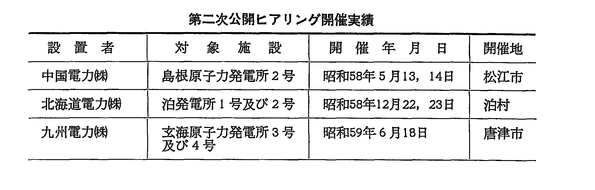第2章 原子力発電
3 原子力発電所の立地関連状況
(1)原子力発電に関する国民の意識
総理府が昭和59年3月に行った「原子力に関する世論調査」では,原子力発電に関し次のような結果が出ている。
将来における主力発電については,「原子力発電」とする者は51%と調査毎に増加の傾向(55年2月 33%,55年11月 47%,56年11月 50%)にあり,原子力発電の必要性等に対する認識の高まりがうかがえる。
一方,原子力発電所に対する不安感については,「心配(不安)に思うことがある」とする者が70%と,近年,原子力発電所は安全に運転されているのにかかわらず前回調査(56年11月 59%)に比べ増加している。不安に思う理由としては,「事故や故障などで放射線(能)が漏れるから」,「放射線(能)が人体や子孫に影響を与えるから」及び「廃棄物の保管や処理・処分などから」が主なものとなっており,また,「放射線(能)は目に見えないから」,「世間一般に危険だと言われているから」等漠然とした不安感を理由として挙げる者も少なくない。
原子力発電所の安全対策については,「十分行われている」と思う者が30%と前回調査(27%)より増加する一方,「そうは思わない」者は38%と前回調査(45%)より減少し,両者間の割合は接近した。なお,「わからない」者は32%(56年11月 28%)となっている。
また,原子力発電を円滑に進めるために重要なこととしては,46%の者が「原子力発電施設の安全対策を徹底させること」を,23%の者が「原子力発電の安全性や必要性を周知させること」を挙げている。
(2)原子力発電所の立地をとりまく状況
近年の原子力発電所の立地の進展状況をみると,昭和58年3月の四国電力(株)伊方発電所3号機以来,電源開発基本計画に組み込まれたものはなく,全体的に電源開発基本計画への組み入れは,電力施設計画の予定に比べ遅れぎみであり,また,電源開発基本計画に組み込まれた後も着工が予定に比べて遅れぎみであること等に示されているように,立地の進展は必ずしも順調とは言えない。
このうち,福島第二原子力発電所原子炉設置許可処分取消請求については,昭和59年7月に福島地方裁判所において第一審判決が言い渡された。判決は原告の請求を棄却し,福島第二原子力発電所原子炉に係る国の設置許可は適法であると認定しており,昭和53年5月の伊方発電所原子炉設置許可処分取消請求に係る第一審判決と同じく,原子力発電の安全性に関する国の主張を認めるものとなっている。
(3)原子力発電所の立地促進
原子力発電所の立地地点の確保は,原子力発電を推進する上で重要な課題である。原子力発電のエネルギー供給上の重要性に鑑み,原子力発電所の立地には最大限の努力を傾注する必要があり,地域の実情を踏まえつつ,電気事業者及び関係行政機関において積極的な取組みが行われている。
また,昭和58年11月の総合エネルギー対策推進閣僚会議において,要対策重要電源に関西電力(株)大飯発電所3号機及び4号機を追加し,その立地の促進を図っている。
イ)広報活動等の実施
原子力に対する国民の理解を求め,その開発利用を一層円滑に推進するため,テレビ・出版物等の活用,講演会・各種セミナーの開催等により広報活動を積極的に行っている。
原子力発電所等の立地を円滑に進めるために,立地予定地域のオピニオンリーダーを対象とした原子力講座等を開催するとともに,原子力発電所立地の初期段階における地元住民の理解と協力を得るため,国自らが広報活動を展開する等の施策を講じている。さらに,地方自治体の行う広報活動等への助成を行っている。
また,電源立地調整官等の機動的活動により,原子力発電所の立地に係る地元調整を推進するとともに,運転に入った原子力発電所の立地県については原子力連絡調整官による地元と国との連絡調整を図っている。
ロ)電源三法の活用
発電用施設周辺地域整備法等のいわゆる電源三法を活用し,引き続き,原子力発電施設等の周辺住民の福祉の向上等に必要な公共用施設の整備を進めるとともに,施設周辺の環境放射能の監視,温排水の影響調査,防災対策,原子力発電施設等の安全性実証試験等を促進し,原子力発電施設等の立地の円滑化を図っている。
また,昭和58年度からは,新たに,次のような施策を推進している。
(i) 「電源立地促進対策交付金」の交付対象施設として,産業の振興に寄与する施設の範囲の拡大(農業,水産業,工業の各試験場等)等使途の充実を図る。
(ii) 「電力移出県等交付金」について,大規模移出県の実態に応じた移出電力量区分の適正化を図る。
(iii) 「原子力発電施設等緊急時安全対策交付金」について,緊急時に必要な防護資機材の整備を行えるよう充実を図る。
(iv) また,「海洋環境放射能総合評価委託費」により原子力発電所等の周辺海域における環境放射能に関する調査及び評価を行う。
さらに,広報・安全等対策交付金の使途の拡大を行う等制度の充実を図る。
さらに,昭和59年度からは,新たに,次のような施策を推進している。
(i) 「電源立地促進対策交付金」について,産業の振興に寄与する施設の範囲の拡大(産業情報センター)等使途の充実を図る。
(ii) 「放射線監視交付金」について交付限度額の引上げを行い,使途の充実を図る。
(iii) 「実用原子力発電施設安全性実証解析等委託費」により,事故の分析評価等ソフト面からの安全性の実証を行う。
また,「交付金事務交付金」について内容の簡素化を図る等の合理化を行った。
(4)公開ヒアリング
通商産業省は,電源開発基本計画案が電源開発調整審議会に付議される前に,原子力発電所の設置等に係る諸問題に関し,第一次公開ヒアリングを開催することとしている。また,原子力安全委員会は,発電用原子炉施設の新増設案件に関し,行政庁の行った安全審査についての調査審議を行うに当たり,当該原子炉施設の固有の安全性について地元住民の意見等を聴取し,これを参酌することを目的として第二次公開ヒアリング等を開催することとしている。
昭和58年4月以降,関係者の協力を得て,3回の第二次公開ヒアリングを開催した。
目次へ 第2章 第4節(1)へ