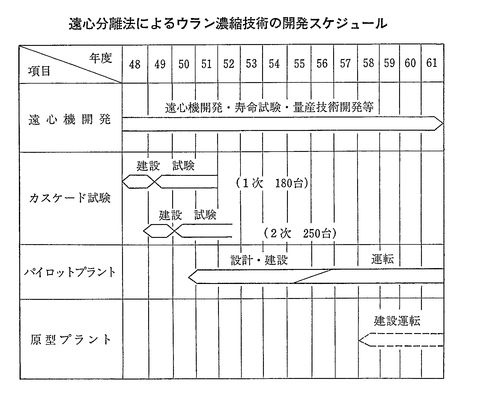第4章 核燃料サイクル
2 ウラン濃縮
(1)濃縮ウランの需給バランス
我が国の原子力発電は,当分の間は軽水炉が主流を占めるものと考えられ,その規模の拡大に伴い,濃縮ウランの需要も増大する見込みである。
このような需要を満たすため,我が国の電気事業者は,米国及びフランスから濃縮役務の供給を受けている。
米国については,現在,米国エネルギー省(DOE)との長期契約により約5,100万キロワット分の発電用原子炉に必要な濃縮役務を確保している。
さらに,フランスのユーロディフ社については,昭和49年に締結された契約に基づき,昭和55年〜昭和64年の10年間に,毎年約1,000トンSWU(約900万キロワット分)の濃縮役務の供給を受けることになっている。
これら既手当分により,昭和60年代中頃までの供給は確保されているが,それ以降の分については,今後,新規の手当が必要となる見通しである。この新規手当の相当部分は,国産により賄っていくこととしている。
(2)ウラン濃縮技術の研究開発
遠心分離法の研究開発については,昭和47年8月,遠心分離法によるウラン濃縮パイロットプラントの建設,運転までの研究開発が「国のプロジェクト」としてとりあげられて以来,動力炉・核燃料開発事業団において強力に推進されている。
昭和52年度から同事業団が岡山県上斉原村(人形峠)において建設を進めてきたパイロットプラントは昭和54年9月に遠心分離機1,000台,昭和55年10月には更に遠心分離機3,000台が運転を開始し,昭和56年末には,遠心分離機合計7,000台による全面運転を開始する予定である。この間,昭和56年4月には,新型転換炉ふげんの燃料の一部として活用するため,3.2%濃縮ウラン約1トンが搬出された。
また,パイロットプラントに続く次の段階のプラントについては,昭和55年度から新たに概念設計が実施されている他,より高性能の遠心分離機の開発等が引き続き実施されており,原子力研究開発利用長期計画に示された昭和60年代中頃の実用工場の運転開始に向けて研究開発が進められている。
なお,上記動力炉・核燃料開発事業団のパイロットプラントを始めとするウラン濃縮技術の開発成果を踏まえ,実用濃縮工場の建設,運転に至るまでのウラン濃縮国産化の進め方について調査審議するため昭和55年10月17日,原子力委員会のもとにウラン濃縮国産化専門部会が設置された。
この調査審議の結果,昭和56年8月,同専門部会は報告書を原子力委員会に提出し,その中で実用濃縮工場の建設,運転に先立って,総合的な経済性,信頼性の確認を目的として原型プラントを建設,運転することが必要であるとし,原型プラントの建設,運転については,民間の積極的協力を得て,当面動力炉・核燃料開発事業団が当たることが現実的であるとした。原子力委員会は,現在,この報告をもとに今後の方針を検討中である。
一方,遠心分離法以外のウラン濃縮技術の研究開発については,民間企業における化学法ウラン濃縮技術の試験研究及びシステム開発調査に対し,科学技術庁及び通商産業省により助成措置が講じられている。
また,レーザー法によるウラン濃縮の研究が日本原子力研究所において進められている。
(3)日豪ウラン濃縮共同研究
昭和49年,豪州にウラン濃縮工場を建設する可能性について日豪共同調査が開始され,昭和53年12月,豪州において濃縮事業が成り立つ可能性があり,その具体的推進のためにより詳細な調査が必要であるとの報告書が日豪両政府によりとりまとめられた。
これを受けて,昭和55年1月,豪州に「オーストラリアウラン濃縮グループ(UEGA)」が設けられ,日本,ウレンコ,ユーロディフ及び米国の協力を得て検討が進められた。我が国においては,日豪ウラン濃縮共同研究専門家会議を設置し,この検討に協力するとともに,動力炉・核燃料開発事業団が濃縮技術に関する情報を提供する等協力を行ってきた。
昭和56年5月,UEGAは,豪州に適した濃縮技術は遠心分離法又は化学法である旨の報告書を連邦政府に提出した。豪州政府は,これを受けて今後早急に技術提供の相手方を選定し,約2年半をかけて本格的フィージビリティ調査を実施することを決定した。
目次へ 第4章 第3節へ