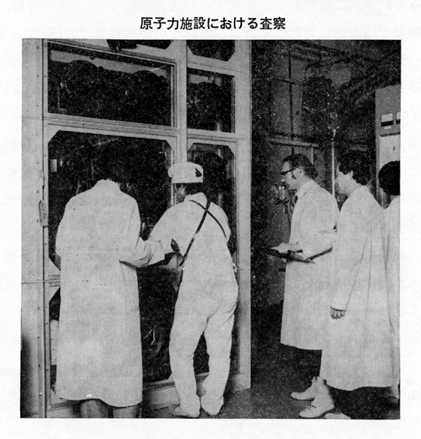2 我が国の核不拡散に対する基本的考え方
我が国は,従来より,原子力基本法の精神にのっとり,自らの原子力開発利用を厳に平和目的に限って推進してきたところである。また一方,核兵器の下拡散に関する条約に加盟し,国際原子力機関との間に保障措置協定を締結し国内の全ての核物質について国際原子力機関の保障措置を受け入れるとともに,核不拡散のための国際的努力に参画する等,国際的核不拡散体制の確立に積極的に寄与してきた。今後ともNPT体制の強化とNPT体制を支える保障措置の充実等を図ることにより核不拡散体制を強化するとともに原子力の平和利用を確保していくことが我が国の基本的立場である。
先にも触れた様に,核燃料サイクルを核不拡散の観点から評価するという試みであったINFCEは昭和55年2月に終了し,保障措置を始めとする核不拡散の手段により,原子力の平和利用と核不拡散は両立し得るとの結論となった。我が国としては,核不拡散の強化により原子力平和利用が妨げられてはならないし,核不拡散と原子力平和利用を両立させる方策は可能であるとの立場を堅持してきており,この結論を受け,世界において,二国間や多国間の場で新たな枠組みに関し今後とも十分な検討がなされるべきと考える。
我が国をめぐる二国間の協議については,当面,日米間の再処理に関する長期的取決めの作成,日豪の原子力協定の改訂等が中心的課題となっている。我が国としてはINFCEの結論,ユーラトム等他の諸国の動向などを踏まえ,我が国の原子力開発利用に支障とならないよう対処する必要がある。
一方,国際原子力機関を中心とする多国間の協議においては,余剰のプルトニウムを国際的な監視の下に貯蔵する制度(国際プルトニウム貯蔵,IPS),使用済燃料を国際的に管理する制度(国際使用済燃料管理,ISFM),原子力資材等の供給保障等の核不拡散と原子力平和利用の両立を目指した新しい国際制度の検討が進められてきており,また,核不拡散上の重要な手段である国際原子力機関による保障措置について改善の努力が行われている。
我が国としては,積極的にこうした二国間の協議及び国際的な枠組み作りの作業に参画するとともに国内的には,国内保障措置体制の整備充実及び核物質防護施策の整備を図り,核不拡散に対する我が国の姿勢を積極的に示していく必要がある。
また,我が国としては,国際的な場において核保有国による核兵器拡大競争を止め,核軍縮と原子力平和利用の推進のため努力していかなければならず,核兵器の脅威を低減させるため核保有国が核軍縮の努力を行うよう,国際的な場で積極的に核軍縮を訴えていく必要がある。
更には,開発途上国を含めたNPT加盟国の拡大,南北両側の適正な相互依存関係の樹立等に向けての二国間,多国間及び国際機関との協力を強化する必要がある。
目次へ 第3章 第3節へ