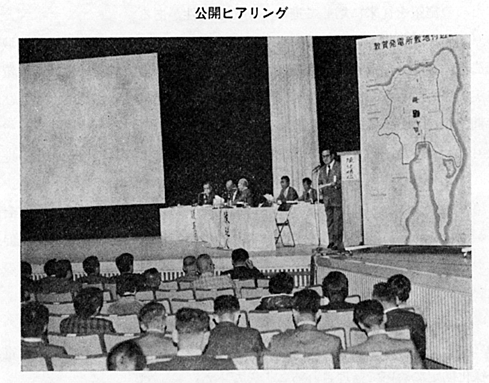第2章 原子力研究開発利用の進展状況
1 原子力発電
昭和54年12月以降の我が国の商業用原子力発電設備は合計21基1,495.2万キロワットであり,国内の総発電設備の約12%を占め,また昭和54年度の総発電電力量の約13.3%を原子力で占めている。また建設中の原子力発電所については11基977.9万キロワットとなっている。建設準備の原子力発電所については,昭和54年度及び昭和55年度上期について,国が定める電源開発基本計画に新たに組み入れられた原子力発電所建設計画が1件もなかったことから3基,315万キロワットにとどまっており,現在我が国の運転中,建設中及び建設準備中の原子力発電所の規模は合計で35基2,788.1万キロワットとなっている。
昭和54年度の原子力発電所の設備利用率については昭和54年3月の米国TMI原子力発電所事故への対応措置として,安全点検を実施したこともあって,上期の設備利用率はPWRを中心にかなりの低下が見られた。しかし,下期については徐々に回復し,昭和55年1月から3月の期間には70%以上の好稼動率を示したため,昭和54年度の設備利用率は,全体として54,6%と,ほぼ昭和53年度並みの水準となった。また,昭和55年度の上半期については,61.6%の設備利用率を示している。
将来の原子力発電規模については,昭和55年11月28日の閣議において,石油代替エネルギーの供給目標として,昭和65年度において,原子力発電により,2,920億キロワット時,原油換算7,590万キロリットルとすることが決定され,この目標を達成するために必要な設備容量は,5,100〜5,300万キロワットと見込まれている。しかしながら,新規立地点などにおいて立地が難航している状況からこの目標の達成のためには,立地点住民の理解と協力を得るための施策を従来に増して進めていく必要性がある。
原子力発電の立地促進対策については,電源三法(発電用施設周辺地域整備法,電源開発促進税法,及び電源開発促進対策特別会計法)による施策の充実に努めており,昭和55年度においては,立地交付金の交付限度額及び交付期間等について拡充が図られるとともに,県,市町村の行う広報活動や安全対策関連業務,防災対策業務等についての国の支援施策の拡充強化が進められることとなった。
第91回国会においては,電源開発促進税法及び電源開発促進対策特別会計法が改正され,石油代替エネルギーの開発利用の推進のため,電源開発促進税の税率を現行8.5銭/kWhから30銭/kWhに引き上げるとともにその使途を拡大し,電源多様化推進のための経費にもあてられることとなり,また,従来から電源開発促進対策特別会計で進められてきた施策は同会計の電源立地勘定において経理されることとなり,電源多様化のための施策は電源多様化勘定において経理されることとなった。
原子力発電関係においても,高速増殖炉等新型動力炉の開発,再処理技術やウラン濃縮技術の開発,原子力発電支援システム開発,あるいは原子力発電施設及び核燃料施設の安全解析コードの改良整備など,実用化段階にあるものについての支援施策及び実用化に近い段階の研究開発プロジェクト等についての施策が,この新会計により,強力に進められることとなった。
原子力発電の安全性に関しては,原子力安全委員会において米国TMI原子力発電所事故の教訓を踏まえ,我が国の原子力安全確保対策に反映させるべき事項として52項目が指摘され,この指摘事項につき,原子力安全委員会の審査会及び各専門部会において精力的な検討が行われた結果,昭和55年6月までにその実施方針が決定された。
これらの検討結果は安全審査に逐次取り入れられるとともに,これらに基づき,安全基準の充実,安全研究の拡充等が,また運転管理監督体制の強化が行われた。さらに万一の事故に備えて,防災対策の充実整備が図られている。
また,原子力安全委員会による第2次公開ヒアリングが,昭和55年1月以降,関西電力(株)高浜原子力発電所3,4号炉,東京電力(株)福島第二原子力発電所3,4号炉,九州電力(株)川内原子力発電所2号炉及び日本原子力発電(株)敦賀発電所2号炉の4地点について実施されており,昭和55年12月には,通商産業省による第1次公開ヒアリングが東京電力(株)柏崎刈羽原子力発電所2号炉及び5号炉について実施された。
さらに,昭和45年11月26日には,原子力安全委員会と日本学術会議の共催により「米国スリー・マイル・アイランド原子力発電所事故の提起した諸問題に関する学術シンポジウム」が開催され,学問的立場から率直な討議が行われた。
また,軽水炉技術の一層の信頼性の向上,検査の効率化等を目的として,通商産業省により第二次改良標準化計画が,昭和55年度終了を目途として,産業界の積極的参加のもとに進められており,その成果は,逐次現在建設中の軽水炉に取り入れられてきている。一方,原子力発電施設についての品質保証をより一層充実させるための活動が官民一体で進められている。
なお,運用期間を終了した原子力施設のデコミッショニング(運転廃止後の措置)に伴う問題については,技術面,安全面,経済面等について,長期的観点から検討が進められており,原子力委員会においては,昭和55年11月28日,廃炉対策専門部会を設置し,廃炉対策の基本的事項について審議することとしている。
目次へ 第2章 第2節へ