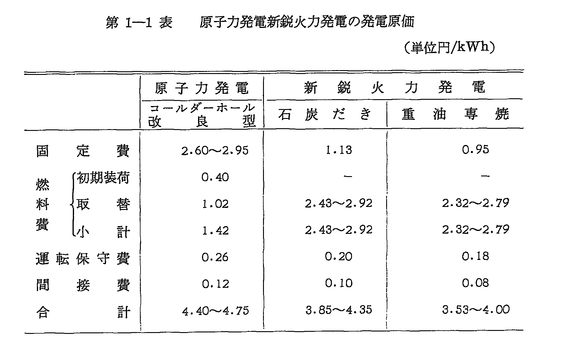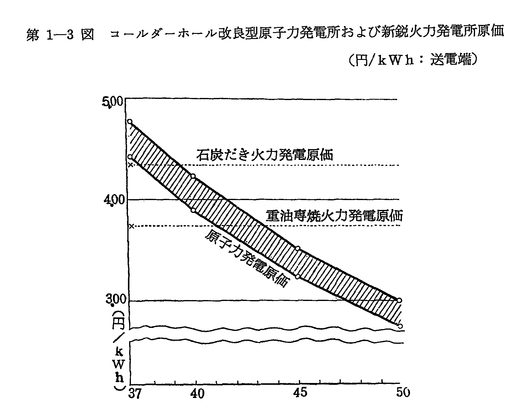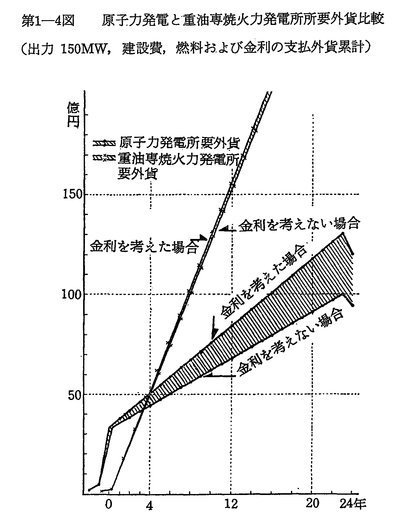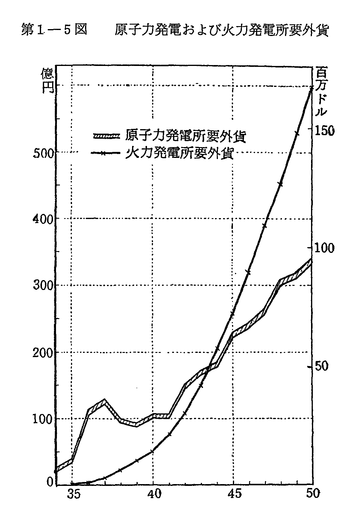§2 原子力発電の経済性
原子力発電についてもつとも関心のあつまるところは,安全性と経済的な評価の問題である。「発電用原子炉開発のための長期計画」においては,経済性に関し,原子力発電の意義として発電原価の低下と所要外貨の節約とを指摘している。
2−1 発電原価
一般に,在来エネルギー源によつて発電原価が大巾にきりさげられることは今後あまりのぞみえないのに対して,原子力発電の場合は発展の余地が大きく長期的にみれば,その発電原価は相当に低下することが予想されている。
原子力委員会では31年秋,英国に調査団を派遣し,コールダーホール型の発電炉の調査をおこなつたが,この調査団の報告によれば,詳細についてはなお検討する必要があるものの,この型の原子炉の実用性は相当明確になつてきており,その発電コストは普通の新鋭火力発電所の発電コストに比し現在のところ若干高いとおもわれるが,将来の火力発電所の燃料費の趨勢などを考慮にいれればすでにいわゆる経済ベースにきたものとかんがえられている。
その後,原子力発電のコストについては引続き検討がおこなわれてきたが,32年12月に原子力委員会は「発電用原子炉開発のための長期計画」において,次のように発電コストの見通しをたてている。
1) 初期段階におけるコールダーホール改良型原子力発電所の発電コストを,新鋭火力発電所と比較して試算すると,(第1-1表)のように原子力発電所はkWhあたり4円40銭〜4円75銭程度であるのに対3,石炭だき発電所では3円85銭〜4円35銭程度,重油専焼発電所では3円50銭〜4円程度であつて,初期段階においてもコストの点で原子力は石炭だきの火力発電に匹敵しうるものとみられる。
2) 原子力発電の場合は一般的に発展の余地が大きく,将来,発電コストが相当大幅に低下することは当然予想されるところであつて,コールダーホール改良型についての大体の傾向は,(第1-3図)のとおりである。一方火力発電の場合は,将来技術的改良による建設費の大幅な値下りはほとんど期待できず,またその燃料についても将来大幅に低下することは期待できない。
したがつて原子力発電は,コストの点からみれば初期においてすでに在来の火力と匹敵し,,さらに数年後においては,最新鋭の重油専焼火力と十分匹敵しうるようになり,それ以後は原子力発電の方が有利になるとみることができる。
2−2 所要外貨
さらに,火力用燃料のうち多くの部分は今後石油の輸入に依存せざるをえなくなり,これに要する外貨も尨大な金額に達することはあきらかなところである。
しかるに原子力発電の場合,核燃料をやはり海外に依存せざるをえないとしても,半製品すなわち精鉱の形で輸入するとすわば,重油専焼火力発電の場合に比してかなりの外貨を節約しうることとなる。いま同規模の原子力発電と重油専焼火力発電をおこなうに要する所要外貨の試算を上記長期計画についてみれば,(第1-4図)のとおりである。
すなわち原子力発電の場合,建設費がたかく,また初期装荷燃料を必要とするため,当初の所要外貨は重油専焼火力に比してかなり大きいが,各年に要する燃料費が少ないため運転開始後数年にして所要外貨の累計は重油専焼火力発電の場合より下回る傾向をしめしている。
さらに,同長期計画においては,発電炉の型式をコールダーホール改良型と仮定し,50年度までに約700万kWを開発する案をとつて,所要外貨を算定し,同一規模の火力発電を開発する場合の所要外貨と比較をおこなつている。その傾向は,(第1-5図)にしめされるが,この図によれば,当初約10年間は原子力発電の所要外貨は火力よりも多額であるが,44年度ごろからは逆に火力の方が所要外貨が増加し,50年度では火力の場合約1.7億ドル,原子力の場合約1億ドルとなる。
毎年度の所要外貨を累計すれば,原子力発電の実施によつて43年度までは約1.6億ドルを余計に必要とするが,さらに50年度までみれば逆に約1億ドル節約しうることになる。
50年度と45年度との所要外貨を比較すれば火力発電による場合はこの間に約2.4倍となるが,原子力の場合には所要外貨は約1.5倍になるにすぎない。さらに将来は原子力発電がますます多く外貨の節約に貢献することとなろう。
以上の試算の結果ながい目でみれば原子力発電をおこなうことによつて巨額の外貨の節約を期待することができる。
目次へ 第1章 第3節へ