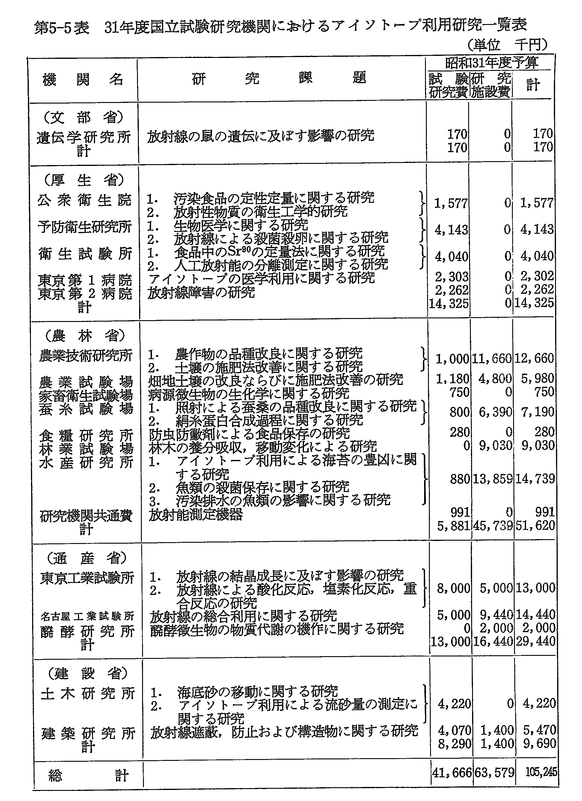§2 アイントープの利用研究
2−1 概説
アイソトープの利用は今世紀の生んだ新らしい分野であり,理学,工業,農業および医学にもたらした効果はすばらしく将来の発展は測り知れないものがおる。その一つの例として,米国原子力委員会が約150のアイソトープ使用会社について調査した結果によると,米国産業界はアイソトープの使用によつて1956年中に鉱工業関係だけでも,3億9,200万ドルの経費が節約されていると推定されている。このほかにも農業および医療においてアイソトープの使用がもたらした効用は大きなものがあるといわれている。とのようにアイソトープは非常に広く利用され,効果をもたらしているが,その潜在的な有用性からみれば,現在の活用度はまだまだ低いといつてよく,今後ますます利用が推進されていけば,そのもたらす将来の成果はきわめて大きいと考えられる。
アイソトープの利用面は.大別すると次の通りトレーサーとしての利用と放射線源としての利用に区分される。
(1)アイソトープは固有の放射線をもつて,どんな条件においても一定の確率的な法則で崩壊しているので,この性質を利用して物質量の定量,年代の推定に用いられる。
(2)アイソトープの化学的性質は安定した同位元素と同じである。したがつて安定した同位元素に微量のアイソトープを混入しておき,その放射線を目印にして追跡すると,化学反応や機構が手にとるように判るわけである。そのうえアイソトープはきわめて微量でも,その存在はガイガーカウンタ,シンチレーションカウンタで容易に判別できるから,有力な測定方法である。したがつて農業,工業,医療等あらゆる方面にこの特性が利用されている。
(3)アイソトープの放射線は各アイソトープについて固有なものでアルフア,ベータ,ガンマ線の種類,強さおよび半減期が定まつている。とれらの放射線は,物質に当ると透過,吸収,散乱,電離等の現象がおこる。これらの特性を適当に利用して,新しい計測機器が作られている。
(4) アイソトープの放射線を大量照射するときは特別な作用効果がある,たとえぱ高分子物質の構造をかえ,化学反応を促進することができる。また,生体細胞に大きな変化を与え,あるいは破壊する作用があるから,品種改良にまた殺菌に利用される。金属その他を透過する力はエツクス線より強くしかも軽便であるので,広く非破壊検査に用いられる。
ひるがえつて,わが国におけるアイソトープの利用状況をみると,25年から年々その利用範囲が拡大され,31年度における各分野の利用状況は附録の一覧表に示す通り広範囲に発展している。なお31年度国立試験研究機関における研究状況は(第5-5表)の通りである。
2−2 理学への利用
わが国においては昭和13年頃から理化学研究所のサイクロトロンで作られた短寿命のアイソトープを利用して,いろいろいろな研究が行われた。たとえばP32,Na24,Cu64などを用いて生理的研究が行われ,また放射化分析によつて金属アルミニウム中の微量の定量も試みられた。
前述の通り,第二次世界大戦の勃発によつてとのような研究は中断され,また終戦後理研のサイクロトロンは破壊されて,との方面は,一時中断されていたが,25年以後アイソトープの輸入開始とともに研究も再開された。
物理学関係では各大学で,それぞれ各種のアイソトープについて,そのべータ線,ガンマ線のスペクトルの研究をおこなつている。また放射線の絶対測定の目的で電気試験所,科学研究所が,それぞれストロンチウム,コバルト,セシウムのアイソトープなどを用いて研究をおこなつている。
化学方面では,東京教育大学で照射したターゲツト物質の精製,九州大学でCo60 を合む試薬を用いてカリウム,夕リウム,インジウム,アンチモンの定量,静岡大学でセシウムおよびルテニウムの無担体分離について研究が行われ,ている。また東京大学,静岡大学,金沢大学,京都大学,大阪市立大学,日本原子力研究所などでは,核分裂生成物の分離精製に関する研究が行われている。標識化合物の製造についても,東京大学,立教大学などで研究され,すでにC14を合む有機化合物50余種を供給する段階に達している。
トレーサーとしての利用は,現在多数の研究室でおこなわれている。その中1,2の例をあげると,電気通信研究所ではSr89とBa140をトレーサーとして酸化物陰極に電子を衝撃させたときに,陰極にSrやBaが飛散する様子を詳細に調べている。東京大学理学部では分光分析のさいに,炭素電極に加えた試料の行動をトレーサーを用いて調べた。名古屋大学理学部ではI131をトレーサーとして,湖水における沃素の行動を調査し,東北大学ではFe59.Co60.Sb125をトレーサーとして,それぞれこれら元素の有機酸醋塩の錯度を決定している。また,東京大学,徳川生物研究所ではクロレラを用いて光合成の研究を行い,京都大学理学部ではCa45で真珠於よび貝殼形成の機構を研究した。放射化分析としては東京大学で科学研究所のサイクロトロンを用いて,酸化ガドリニウム試料および酸化イツトリウム試料中に不純物として含まれているジスプロシウムを定量した。またニオブ,タンタルの混合物中の両者の定量,写真乾板中の銀の定量などに成功した。
また国立科学博物館,科学研究所,名古屋大学の共同研究で,ベータ線の後方散乱を用いて,わが国の古代文化財の調査を行ない,古代ガラスおよび古磁器のうわぐすりの中の鉛の定量や奈良の大仏の鍍金の厚さなど,貴重な試料を損傷することなくおこなうことに成功した。
2−3 工業への利用
アイソトープは,トレーサーとレて用いる研究室での研究には相当使われているが,工場の現場での利用はまだ充分といえない。その最大の原因は,これを取扱う技術者の不足によるものと思われるが,工場汚染,放射線障害防止などの問題もある。現場向きの実用的な軽便で安定な測定器の発達が深く望まれ,るのであるが,現状はようやくその方面の研究が緒についたところである。
土木方面では,東京大学生産技術研究所と北海道開発局が共同して,北海道苫小牧築港に関連して,海底の砂が海流でどう動くかを放射性亜鉛を含んだガラス砂を使つて29年以来実験し,港湾計画上有益な資料をえた。また建設省では洪水のときの石の移動を,石にCo60をつけて利根川で観測している。電源開発株式会社土木調査部では28年からダムの漏水の調査をおこなつている。また水圧鉄管中をどのくらいの早さで水が流れるかをCo60 を使つて測定し,発エ電所水車の効率測定に貢献している。そのほか農業土木方面でも,アイソトープ投入による流量測定や漏水調査は,漸次各所で行われるようになつてきた。
京都大学工学部土木工学教室では上水道の貯水池などを水が通過するのに,どのくらい時間がかかるかをI131を使つて,興味のある研究をおこなつている。
工業的規模で実験をおこなつたものに,放射性元素のラドンガスを使つての1,000トン溶鉱炉内のガスの分布,速度の研究がおる。またガラス溶融炉や作業炉内のガラスの流れを従来満足に測る方法はなかつたが,Co60,Zn65を使つて測定し,種々の貴重な資料をえている。
アルコール発酵工業に関連して,東京大学生産技術研究所では蒸溜管内の物質の移動状況をP32を使つて研究し,東京工業大学では充填層中の物質の流動状態を,東京大学ではかくはん槽中の流体の流速分布をCo60で測定した。
磨耗の研究もアイソトープを使つて盛んになつてきた。芳香族化合物の減耗性の研究(大阪大学工学部),ゴムの磨耗量の測定,放射体によるデロンの磨耗の研究(名古屋工業技術試験所)などがおこなわれている。
ガラスに対する亜鉛イオンの吸着や亜硫酸ガスの吸着写真乳剤,ポリ塩化ビニールの水洗効果,固体表面の油の除去や洗浄効果,耐火レンガの消耗破損に関連して鉄,カルシウムなどの拡散,ゴムの中の単体硫黄の拡散,水銀中の自已拡散および水銀陰極の流動状態,溶接棒の被覆剤中の硫黄の溶接金属への移動,アルミニウム中の鉄の挙動,アルミニウム中の不純物としての鉄の分布,加工,熱処理の影響,銅精製時の不純物の行動,亜鉛メツキのクロム酸処理薬品の生成機構,オートラジオグラフ用の感光剤など各方面にわたり,非常に広範囲にアイソトープをトレーサーとした研究が進められている。
アイソトープを線源として利用する部門では,鋳物や熔接部分の欠陥の非破壊検査が圧倒的に多く,次は厚み計,液面計,積雪計などへの利用である。現在Co60を使つて実際の現場作業で欠陥検査を行なつている工場は全国に多数ある。たとえば造船関係では主要な造船所は全部使つており,とくにCo60は透過力が強く持ち運びが簡単なので,従来のエツクス線に代つて使用されている。
また無接触非破壊で遠隔的にその厚み,濃度,液位などを測るために放射線を利用した工業計測器は全産業分野で,工程の管理,作業のオートメーション化に利用されはじめている。ベータ線厚み計を例にとると,すでにわが国でゴム,プラスチツク,紙,金属等の産業で数十例に達し,品質の向上,コストの低下に役立つている。
放射線化学的な利用については,科研,東京大学,東京工業大学,学習院大学,中央大学の共同研究がある。すなわち,放射線による高分子物質の変化に関する研究で,ポリエチレン,ポリ塩化ビニール,ポリビニールアルコールの放射線照射の効果をCo60からでるガンマ線と,サイクロトロンで加速された重陽子線を用いて調べている。また京都大学工学部では,空気の共存の影響に注目して放射線による醋酸ビニールの重合反反応およびポリ醋酸ビニールの放射線による変性について研究し,従来から明瞭でなかつた諸点を明かにするこよができた。これによつて僅少のCo60などを用いる放射線化学を,各種の高分子物質に適用して,学術上ならびに工業上重要ないくつかの課題.を探求する道がひらかれた。その他民間における高分子物質の変性の研究を行うために,民間企業の共同出資による日本放射線高分子研究会が発足している。
2−4 農業への利用
施肥法を改善するため,各種の肥料試験が行われているが,P82を利用するアイソトープ追跡技術が発達したので,従来どうしても不明であつた点-たとえば土壌中の燐酸と肥料中の燐酸は,ともに天然のP31でおつて,双方はどんな方法でも区別できなかつたーが解明されたのでおる。農林省農業技術研究所ではP32を使つて,土壌肥料の研究がいろいろと行われている。その結果によると,老朽化秋落水田に施肥した燐は,土壌がこれをとらえる力が弱く,下に溶脱することがわかり,その結果,この種の水田では,燐を基肥ばかりに集中して与えず,分施する方法がとられて効果をあげている。
また同じ秋落土壌についてS35の追跡研究によると,従来過燐酸や硫安などに含まれる硫酸根だけが,土壌中に生じる硫化物の源となると考えられていたが,実は土壌中に発生する硫化物の約半分は土壌自体の有機物から発生していることがわかつた。したがつてこの老朽化田対策としての客土は,従来にも増して重要視されている。またN15を用いた土壌や肥料の試験が行われ,従来の窒素肥料吸収率が高すぎていたこと,水稲が植えられてから刈り取られるまでの間に,予想外に大量の地力窒素が働いていることなどがわかつた。
品種改良は,アイソトープからでる放射線などを利用すると,従来の方法に比べて,突然変異の頻度が,遥かに高いので,世界各国で盛んに研究されている。わが国ではアイソトープのうちでベータ線を出すP32のように半減期が短かく,植物に吸収され易いものを使つて,種子のときか,または生長の初期に吸収させて品種改良が行われている。これは小規模で実験室内で処理できる研究でおり,稲については,農業技術研究所で26年以降おこなわれている。すなわちP32を稲の種子に吸収させて稲の突然変異を誘発させ,早生,晩生,短稈,密粒,大粒,その他多くの変異体を作つた。これらの中から有望系が見出されている。このようにわが国において,アイソトープ利用による稲の品種改良は有望となりつつある。今後わが国でもガンマフイールドが設置されたり,研究用原子炉が稼動するようになれば短時間に,重要農作物の品種改良を達成する可能性が高まるものといえよう。
わが国では経費や設備の関係から,米国のように牛などの大動物を使用する研究はおこなわれず,今までに鶏,家兎などの小家畜を使つて, 「産卵鶏におけるカルシウムと燐の代謝」「鶏卵のふ化時におけるカルシウム,燐の利用」「家畜のいわゆる骨軟症のカルシウム,燐代謝」「産卵鶏における種々の化合形態の窒素の有効性」などの研究がおこなわれている。
わが国ではかなり以前からP32を使つて,蚕体生理の研究が始められている。
戦後その研究は盛んになり,蚕糸試験場を中心として,P32の蚕体内での行動,各器官への分布,透過性,無機態燐から有機態燐への変化など一連の実験がおこなわれている,また絹糸蛋白質が蚕体内で合成される機構をC14で追求して,貴重な成果をえている。
海洋の生産力を知ることは,水産の研究として大切なことであるにも拘らず,従来は適当な方法がなかつたが,C14で測ることができるようになつた。
気象研究所では,28年から,わが国周辺の海洋の生産力を測定し始めた。東海区水産研究所では,戦前から浅草のりの豊凶の原因を研究してきたが,30年から,C14を使つてこの研究をさらに発展させている。すなわち浅草のりは豊凶の差が大吉いが,多数ある原因の中で水質の差が大きく,のりの豊凶を左右することをC14を使つて証明した。
放射線照射による食品の防腐保存の研究は,東京水産大学を中心に,28年からCo60の照射装置を使用して研究が開始されている。すなわちかまぼこ,鮮魚肉,サメ肝油を試料として,これにガンマ線を照射し,相当基礎的なことが明かにされた。
2−5医学への利用
基礎医学部門でアイソトープを使つての研究は非常に盛んでありその研究論文は多数あるが,そのうち2, 3を例示すれば,核酸代謝,アルカロイドの生合成機構,アミノ酸の生合成,結核菌の毒力,結核菌の感染径路,放射線の白血球数ならびに白血球機能におよぼす影響などが主として大学を中心におこなわれている。
医学の実際面への利用としては,診断上への利用と治療上への利用とがある。
前者の例としては,,I131が選択的に甲状腺に集ることを利用して甲状線機能を診断することが各地の病院で実際におこなわれているほか,悪性腫腸の診断,血液の寿命と貧血の診断,脊髄液の検査が盛んにおとなわれている。
アイソトープの治療上への利用は(1)内用療法(2)近接照射(3)べータ線による外面照射(4)大量遠隔照射に分けられる。
1131は甲状線機能冗進症と診断されたものの治療に用いられている。国立東京第二病院を例にとれば,27年以来,甲状腺機能亢進症200余例に放射性沃度を投与し,全治80%という好成績を収めた。P32.Na24は,燐酸ナトリウムの形で注射すると,骨髄,肝臓,牌臓などに蓄積される白血病や真性多血症に治療効果が高く,とくに真性多血症には有効である。Na24も塩化ナトリウムの形で用いられている。またP32は腫瘍部分によく集ることから,骨肉腫や骨に移転した癌の治療に用いられており,Au198による悪性腫瘍の治療は30年以来臨床上に使用され,数カ月以上の経過を見た症例が25例におよんだ。そのうち著効11例,好転8例と好成績をえている。
近接照射用のアイソトープはC60,C8137, TaIS2,Au198など,各種の形式で用いられている。
ベータ線による外面照射はP32,Sr90,Y90が強力なベータ線を出すので,これを皮膚の単純性血管腫(赤おざ)色素性母斑(黒あざ)に照射して治療するほか,眼科でもSr90強線源を用いて,結膜,角膜の疾患に使用している。27年から31年の間に外来患者1,000余例のうち4回以上治療をおこない,経過の明かな赤あざ431例,黒あざ369例,計800例の患者に治療を行い,良好な治療成績をえている。
大量遠隔照射はCo60,Cs137,によつて,多数の病院で実際にガンの治療に好成績をあげている。従来のx線照射では深部に発生するガンは治りにくかつたが,肺,前立腺,胃,食道などのガンに盛んに利用されている。
C060による大量遠隔照射装置は,28年全国で僅か167キュリーであつたが,31年には,4,500〜5,000キュリーとなつた。とのガンマ線量に相当するラジウム量は6,700〜7,500gであつて,かつての日本における医療用ラジウムの総量10数グラム,に比較すると,隔世の感がある。今後は基礎医学,臨床医学ともにアイソトープの利用は益々拡大されるものと思われる。
目次へ 第5章 第3節へ